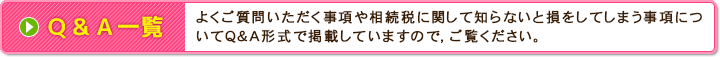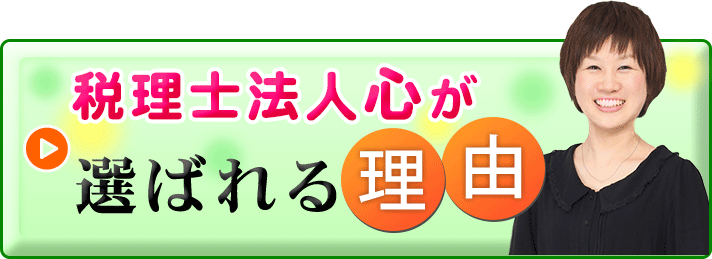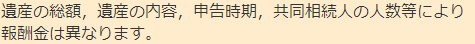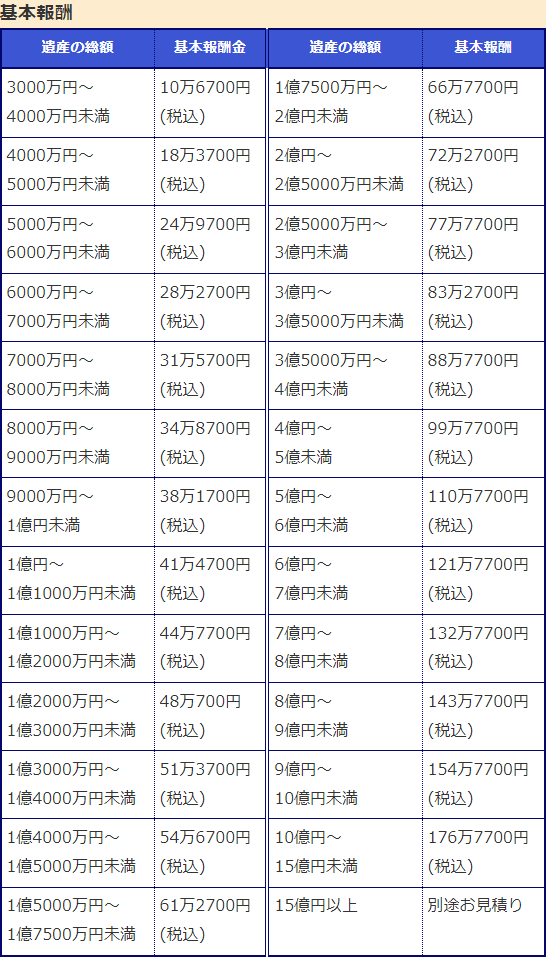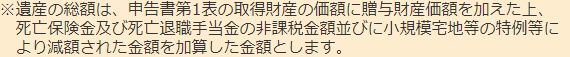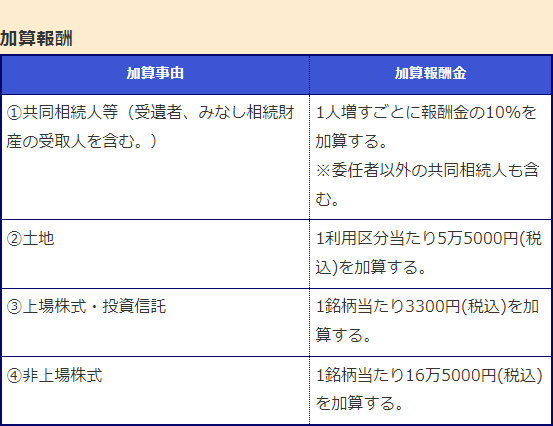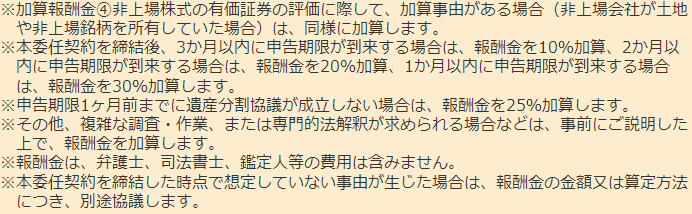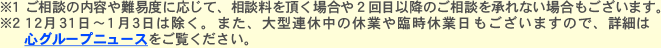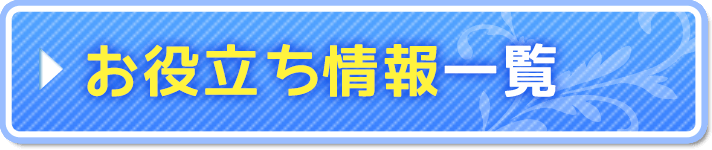「その他」に関するお役立ち情報
生前贈与の失敗事例
1 生前贈与は確実に行う必要がある
相続税対策として、生前から相続人や相続人以外の家族に対して生前贈与を行っているというケースが多くみられます。
たしかに、生前贈与はよく行われている相続税対策の手法ですし、しっかりと行えば大きなメリットがある方法ですが、税務署からの調査の対象となり、「贈与がなされたとは認められない」という指摘を受けることが多い分野でもあります。
生前贈与の失敗事例とその対策をここでいくつか挙げようと思います。
2 受贈者の口座とは認められない場合
生前贈与は、暦年贈与の非課税額である年間110万円を意識しながら、対象となる方の預貯金口座から受贈者の口座に対して振り込まれるなどの方法で資金が移動するのが一般的です。
受贈者の口座は、名義が受贈者になっていますから、一般的な意識からすると、「その人の口座にお金が振り込まれたのだから、その人のものとなった」と考えられそうです。
しかし、法律の考え方からいうと、口座の預金が誰ものかを判断するうえで、預金の名義は重要な判断要素の一つですが、それのみで決まるわけではなく、資金を負担したのが誰であるのか、通帳などの口座を管理していたのは誰か等の考慮要素をもとにして、判断されるものです。
ここで、受贈者の口座が、対象となる方に管理されており、受贈者が自由に引き出すなどの管理ができない場合には、その口座の預金は受贈者のものではなく、対象となる方の財産であると判断されることになります。
すると、その口座の預貯金も相続財産として扱われてしまうため、生前贈与による相続税対策をした意味がなくなってしまうということになります。
「子どもに渡してしまうと、無駄に使ってしまうから、親が管理しておく」という考えだと、相続税対策としては非常にリスクが高くなるといえます。
確実に「受贈者に渡した」とするためには、受贈者が普段から利用している口座に入れるなどの方法をとって、贈与が確実になされたと言えるようにしてください。
3 連年贈与と扱われる場合
生前贈与による相続税対策が行われる場合、年間110万円の暦年贈与の非課税額を利用されることは上で述べました。
ここで、たとえば、親から子どもに、毎年1月1日に110万円の贈与を10年にかけて渡していたとします。
この際に、上で述べたように、子ども自身が管理する口座に入れていればそれで安心というわけではありません。
なぜなら、「親から子どもに1100万円の贈与がなされ、毎年1月1日に分割して贈与金が支払われていただけである」(このような贈与は連年贈与と呼ばれています)との指摘を税務署から受けるおそれがあるのです。
そうすると、当初の贈与が行われた際に1100万円の贈与が行われたと扱われてしまいます。
これを防ぐためには、親から子どもに資金を渡す日を毎年ずらしたり、資金の額を毎年変えたりすることで、連年贈与であるとの指摘を防ぐようにしましょう。